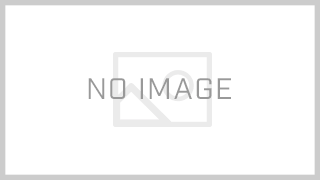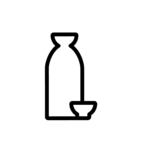日本酒はどのくらいの期間保存できるかご存じでしょうか。
開栓前と開栓後の日本酒では、保存期間にどのくらい違いがあるのでしょう。
焼酎やワインのビンテージのように、日本酒も長期保存するとおいしくなるのでしょうか。
日本酒を購入したりもらったりする中で、疑問を持つ方も多いのではないかと思います。
この記事では、日本酒がいつまでおいしく飲めるのか、おいしく飲める期間の目安について解説します。
また、日本酒それぞれの銘柄本来の味や香りを堪能するための保存方法のポイントについても見ていきます。
日本酒の保存期間の豆知識①】日本酒に賞味期限はあるの?
まず、日本酒には賞味期限はありません。日本酒はアルコール度数が高いので、アルコールの殺菌力により細菌は繁殖することができません。つまり日本酒は長期保存が可能で、健康を害するような腐敗がないのです。この事から食品表示法により日本酒には賞味期限表示が免除されています。この食品表示法による免除は日本酒だけでなく、ワインやウイスキー、焼酎などの酒類全般において適用されています。
しかしながら賞味期限がないことと、いつまでも日本酒をおいしく飲むことができることがイコールであるという事ではありません。後述しますが、保存方法によっては短期間で日本酒の風味が劣化していくことが、実はよくあります。日本酒を楽しむために注意することは、いかに日本酒が腐らないかではなく、いかに日本酒をおいしく飲めるかという事に尽きるのです。
【日本酒の保存期間の豆知識②】ラベルに記載されている製造年月について
日本酒は、食品表示法によって賞味期限表示が免除されている代わりに、製造年月の表示が義務化されています。
では、この製造年月とは一体何を意味しているのでしょうか。
これは、日本酒が造られた年月ではありません。酒蔵からスーパーマーケットや酒屋さんに出荷した日を表しています。昔は瓶詰めした日を表していたようですが、最近では瓶詰めして貯蔵されているケースが多くなっていて、こんにちでは日本酒に記載されている製造年月は、リリース日が書かれていることが多いようです。
開封前の日本酒の保存期間は?
未開封の日本酒の場合、適切な保管方法であれば保存期間は気にしなくてよいでしょう。だいたい1年以内に飲むのが通説となっています。
細かく見ていくと、製造方法によって保管期間は違ってきます。その製造方法は2つに分けることができます。「火入れ」という加熱処理が行われているか、「火入れ」という加熱処理が行われていないかの2つです。
日本酒の多くは、日本酒を造った直後と出荷する直前の2回にわたり「火入れ」という加熱殺菌処理を行います。搾られた新酒を加熱することで、酵母の発酵がとまり、飲み頃の味わいと風味を長く保つことができるようになります。「火入れ」を2回行われる本醸造酒などは、発酵をしっかり止めることで、日本酒の品質が安定します。種類によっては、火入れを1回しか行わない日本酒もあります。
これに対し加熱処理をせずに出荷する日本酒を生酒と呼びます。
以下では、日本酒の種類によって保存期間はどう異なるのかをご案内します。
本醸造酒、普通酒の場合
本醸造酒や普通酒は、製造年月から約1年以内が適切な保存期間です。「火入れ」を2回行い、醸造アルコールを添加するなど、アルコール度数をきっちり管理しているため品質には安定感があります。
純米酒、吟醸酒、生貯蔵酒の場合
醸造アルコールを添加しない純米酒や、繊細な吟醸香を持つ吟醸酒、火入れを1回しか行わない生貯蔵酒は、やや保存期間が短くなり、おいしく飲める目安は製造年月から9か月ほどになるでしょう。
生酒の場合
「火入れ」を一切行わない生酒は、火入れをしない分、新鮮な風味を楽しむことができます。しかしその代わりに香味の劣化のスピードも速いので、生鮮食品と同じように、できるだけ早く飲むのがおすすめです。
ここでご案内したことは、全て冷暗所で保存されていることが前提になっています。適当に長い間放置していると日本酒の味や香りは変化、劣化していく可能性があるので後述する保存方法でしっかり管理しましょう。
開封後の日本酒の保存期間は?
開栓したら、基本的には日本酒の品質の劣化というのはどんどん進んでいくものだと思ってください。これは火入れしていても、火入れしていなくても変わりません。また、開栓して液量が少なくなるにつれて空気に触れる面積も増えるので、日本酒は酸化して品質は劣化していきます。
一般的な日本酒の開封後の保存期間の目安
とはいえ、あまり神経質になって日本酒を楽しめなくなるのも本末転倒になってしまいます。目安としてざっくりいえば、日本酒を購入した後、自宅の普通の冷蔵庫で保存する場合は、生酒やスパーリングタイプでなければ、日本酒を開けてから1ヵ月くらいが平均的な目安となります。
スパークリングタイプ、生酒の開封後の保存期間
生酒や瓶内二次発酵させたスパークリングタイプなど、フレッシュさが売りのお酒は、早めに飲んだ方がフレッシュさをより感じる事ができます。スパークリングタイプを選ぶときは、基本的に栓を開けてからすぐに飲み切ってしまう方がいいでしょう。生酒も変化が速いので、できるだけ早めに飲むのがおすすめです。
【日本酒の保存期間が過ぎた後】古くなった日本酒はどう活用する?
なかなかデリケートな日本酒ですが、毎度毎度、日本酒を早めに飲み切れないこともあると思います。また、古くなった日本酒をそのまま飲むと「どうも風味、味が…」と躊躇するときもあると思います。ここでは、日本酒が余ってしまった時、捨てずに活用できるおすすめの方法をご紹介します。
料理酒として使う
古くなった日本酒は、料理酒として使いましょう。実は、料理本のレシピに書かれているお酒は、食塩などが入っている料理酒ではなくシンプルに日本酒のことなのです。日本酒を煮汁にしみこませれば、臭みの成分を抑えたりアルコールとともに蒸発させたりする効果があります。また、肉や魚を柔らかくしてくれる効果も。炒め物に日本酒を少し足すだけでコクが出ますし、どんな料理に入れても邪魔することはありません。
日本酒風呂にする
お風呂に少量の日本酒を加えて、贅沢に「日本酒風呂」にしてみるのもおすすめです。新陳代謝が促されるので、体が温まりやすく、お肌がしっとりすることで人気があります。
注意点は、風呂釜を傷めないように、追い炊きはしないで使用後はすぐに排水しましょう。
化粧水として使う
小さなスプレーボトルに日本酒を入れて化粧水代わりにするのもなかなか良いです。作り方は精製水と日本種を混ぜ、そこにグリセリンを混ぜるだけです。
日本酒はアルコール度数が高いので使う前にアルコールを飛ばしておくことで肌に優しくなります。防腐剤が入っていないため、早めに使い切りましょう。
炊飯に利用する
お米を炊くときに、日本酒を少量加えて炊くと、炊き上がりにツヤが出て、甘みが増します。冷めたご飯を温め直すときも、日本酒を少量加えることで、ふっくらしたご飯になります。日本酒を入れて炊いたお米は、炊き上がったころにはアルコール成分はすべて沸騰してなくなっています。
お餅にスプレーする
カチカチに堅くなったお餅に日本酒を吹きかけてしばらく経つと、お餅が柔らかくなります。
日本酒の保存方法 3原則
いままで日本酒の保存期間についていろいろ見てきましたが、ご紹介した保存期間は日本酒がしっかり管理されている、というのが前提でした。
ここでは、日本酒を上手に保存するためのポイントについてみていきます。
紫外線や光を避ける
日本酒は紫外線にさらされると必ず劣化してしまいます。短時間日光に当てるだけでも日本酒の品質に大きな影響があります。日光はもちろんのこと蛍光灯などの光にも要注意です。とにかく光を避け、暗いところで保存する必要があります。厳密にいうと冷蔵庫の開閉時の照明もできれば避けたいところです。多くの方がご自宅にそんなスペースなんてない、と考えると思いますが、新聞紙やアルミホイルなどで日本酒を包んで保管するのが一番身近なやり方かなと思います。
冷蔵保存
日本酒は高温を苦手としています。高温多湿を避けできるだけ低い温度の環境で保管することが求められます。一般的にはやはり冷蔵庫での保管がベストと考えるべきでしょう。
立てて保存しよう
ワインはコルクの乾燥を防ぐために、横にして保管することが推奨されていますが、日本酒の場合、横に寝かせるのはNGになっています。日本酒は空気に触れることで、味わい、風味が劣化していきます。空気と触れる面積を最小限にするために寝かせずに立てて保存しましょう。
【日本酒の保存期間を活かすために】日本酒を上手に買う方法
これまでの日本酒の管理は、常温か半冷蔵が常識でした。皆さんもスーパーや酒屋さんでは常温で並べていたり、半開きの冷蔵庫に置いていたりしたのを見たことがあると思います。しかしこのような管理方法では、皆さんが手に取るころには日本酒の味わいが劣化している可能性が高いです。しかしだからと言って身近に、ライトがない冷蔵庫に日本酒を保管している、照明にUVカットのフィルムが巻いてある、そもそもショーケースには見本の空瓶しか置かずに購入時に奥の冷暗所から日本酒を持ってくる、といった対応をしている日本酒専門店がある人の方が少ないと思います。
そこで、少しでも日本酒をおいしくいただくために、チェックしていただきたいポイントが一つあります。それは、前述した日本酒のラベルに記載義務のある「製造年月」を必ずチェックしてから購入する、ということです。製造年月はいわば、日本酒がそのお店に嫁いできた日付を表しています。その日付が古ければ古いほど、その売り場に来てから時間が結構経っているので、その売り場の環境によっては劣化がかなり進んでいる可能性があります。
とにかく製造年月が新しい日付の日本酒を購入してみてください。そして購入した後は、できる範囲で日本酒の保存方法3原則を守りながら、素敵な日本酒ライフを楽しみましょう。